
徳川家康の粗食健康法
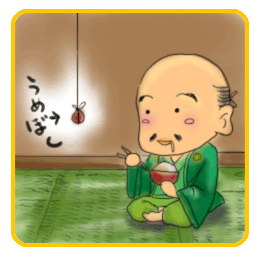 徳川家康は、幼少から人質として他国にとらわれていたが、桶狭間の戦いを機に自由を手に入れ、それからは、織田信長の同盟者として三河統一を目指した。
徳川家康は、幼少から人質として他国にとらわれていたが、桶狭間の戦いを機に自由を手に入れ、それからは、織田信長の同盟者として三河統一を目指した。
また、1600年の天下分け目の関ヶ原の合戦では、大勝利をおさめ、その後の徳川幕府300年の基礎を築いた。
では、なぜ徳川家康はこれほどの大人物になれたのだろうか。それは一重に、織田、今川と渡り歩いた、およそ12年にわたる、人質生活での苦労がそうさせたと言うほかあるまい。その人質生活のときに徳川家康(当時は竹千代)は忍耐と質素倹約を身につけた。忍耐については、後世の例え話、「鳴かぬなら、鳴くまで待とう、ほととぎす」で、知られるように待ち続けて天下をとった。また、質素倹約については、かんでいた鼻紙が風で飛んでも、それを追って行くというほどの、しつこさであった。
そしてさらに徳川家康は粗食であり、三河の岡崎城にいた壮年の頃は、毎年、夏中は麦飯を食べていたと言う。この粗食こそ徳川家康の健康法で、戦国時代の武将にも関わらず、75歳まで生きてたのも、このためであろう。
日本人は昔から材料の持ち味をいかし、淡白なメニューを開発してきたので、こういった粗食は、体内の消化・吸収・燃焼・排泄の代謝作用に負担をかけず、体調を調えてくれるのだ。
現代でもヘルシーで健康食との呼び声の高い日本食。徳川家康は、その辺のことを知りつくしていたのかは分からないが、まさに 粗食健康法を実践し、健康を維持していたのである。
参考文献 「戦国名将、人物を知る辞典」 監修山本七平 永畑恭典

